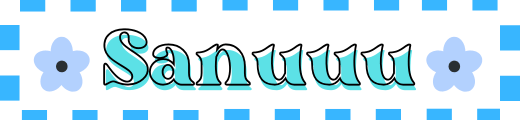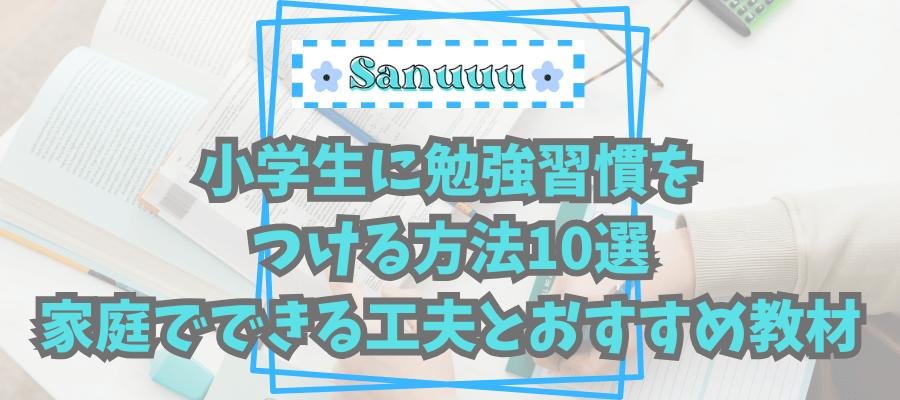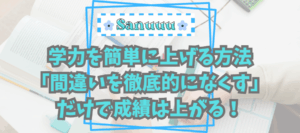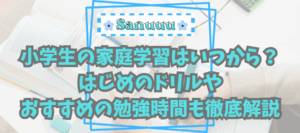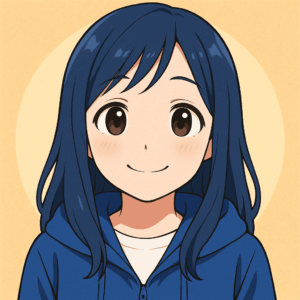「うちの子、なかなか勉強の習慣がつかない…」と悩む保護者の方は多いのではないでしょうか。
小学生の時期は、勉強への姿勢や学習習慣を身につける大切なタイミングです。
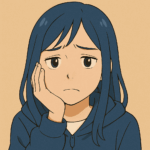
しかし、毎日決まった時間に机に向かわせるのは簡単なことではありません。
我が家でも3人の小学生を育てる中で、宿題が終わればすぐに遊びたがる子や、集中が続かない子に頭を悩ませてきました。
けれども、ちょっとした工夫や子どもに合った教材を取り入れるだけで、勉強習慣は少しずつ定着していきます。
化できれば、学力アップはもちろん、自信や生活リズムにも良い影響を与えてくれます。
この記事では、具体的な「小学生に勉強習慣をつける方法10選」と、我が家で実際に役立った教材を紹介します。
ぜひご家庭でも参考にしてみてください。
小学生に勉強習慣をつける方法10選
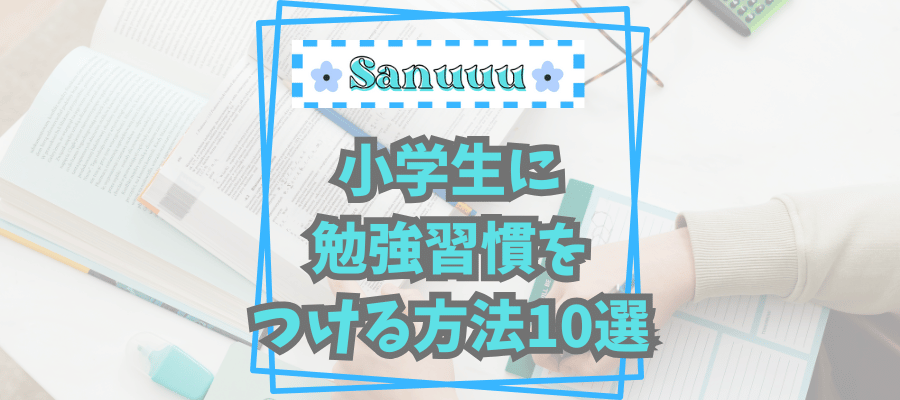
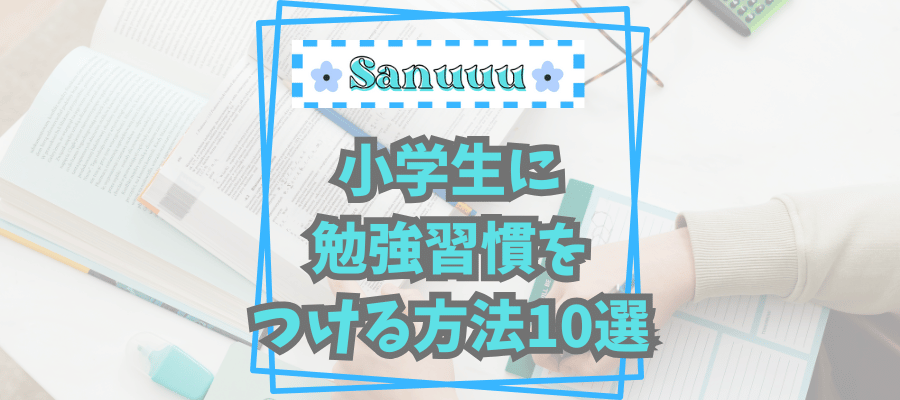
小学生にとって、勉強は「やらされるもの」になりがちですが、早い段階で習慣化しておくと大きな力になります。
毎日少しずつ机に向かうことが当たり前になると、テスト前に慌てる必要もなく、学年が上がっても自然に学習を続けられます。
私自身も3人の子どもを育てる中で、勉強習慣がある子とそうでない子では大きな差がつくと感じています。
勉強が苦手な子でも、工夫次第で「やってみよう」という気持ちに変わります。
ここでは、今日から実践できる「小学生に勉強習慣をつける方法」を10個ご紹介します。



無理なく、楽しく、そして自信につながる習慣づくりのヒントにしてください。
①毎日の学習時間を固定する
学習習慣をつける一番のコツは「時間を決めること」です。
- 学校から帰っておやつを食べた後
- 夕食の前
- 夕食の後
- 風呂の後など
毎日同じタイミングで机に向かうと、自然に習慣化できます。
我が家でも「ご飯の前にドリルを1ページ」と決めたことで、子どもたちは勉強を生活の一部として受け止めるようになりました。
時間が決まっていると親も声かけしやすく、
- 「今日はやった?」
- 「もうすぐ時間だよ」
とリズムをつくれます。
最初は短時間からでも大丈夫。固定化することで「勉強=当たり前」という感覚が育ちます。
②学習環境を整える
- テレビやゲームを消す:気が散る要素を排除して集中できる空間にする
- 机の上を整理する:勉強道具だけを置き、不要なものは片付ける
- 照明を明るくする:手元が暗いと集中力が下がるので、デスクライトを活用
- 姿勢に合った椅子と机を用意する:高さが合わないと疲れやすくなる
- リビング学習なら親の目が届く位置にする:低学年は安心感が持てる
- 音の工夫をする:静かな環境が理想だが、集中できる子は環境音や音楽も効果的
- 文房具を取りやすくまとめておく:探す時間を減らし、学習開始をスムーズにする
- 学習専用スペースを決める:ここは勉強する場所、という意識づけをする
子どもが集中できない原因の一つが、勉強環境です。
テレビがついていたり、おもちゃが視界に入ると気が散ってしまいます。
我が家でも最初はリビング学習でしたが、テレビを消し、机の周りから漫画やゲームを片付けるだけで集中度が上がりました。
低学年のうちはリビング学習でも十分ですが、親の目が届く範囲に「静かな勉強コーナー」を作ると良いです。
勉強に使うものだけを置いて、気が散る要素を減らすことがポイント。
環境を整えることで、子どもは自然と学習に意識を向けられます。
③学年×10分の短時間から始める
| 学年 | 勉強時間の目安 | 内容の例 |
|---|---|---|
| 小学1年生 | 10分 | 音読・簡単な計算 |
| 小学2年生 | 20分 | 漢字練習・計算ドリル |
| 小学3年生 | 30分 | 宿題+文章題や読書 |
| 小学4年生 | 40分 | 演習ドリル・理科や社会の基礎 |
| 小学5年生 | 50分 | 複数教科の復習・応用問題 |
| 小学6年生 | 60分 | 中学準備・英語や総合問題集 |
小学生の家庭学習は「学年×10分」が目安といわれています。
1年生なら10分、3年生なら30分。長時間やろうとすると子どもも疲れてしまいますが、短時間なら集中して取り組めます。
我が家でも1年生の子は10分間の計算ドリル、6年生の子は1時間を目安に勉強しています。
大事なのは「短くても毎日続けること」。時間が短くても習慣になれば、学年が上がるごとに自然と学習時間を伸ばせます。



「今日は10分だけ」と思うと子どもも気楽に始められ、勉強への抵抗感を減らせます。
④宿題+ドリル1ページを習慣化
「宿題をやれば終わり」ではなく、プラス1ページだけドリルを取り入れると基礎力がぐっと伸びます。
我が家では「宿題が終わったらドリル1ページ」と決めています。
ほんの5分程度ですが、これが習慣になると応用問題や読解力も身についてきます。
おすすめは算数ドリルや漢字練習帳。
低学年は計算や書き取り、中学年以降は文章題や読解を足すと効果的です。
宿題+αの学習は「できる子」と「勉強が苦手な子」の差を埋める鍵にもなります。
⑤ご褒美や達成感を取り入れる
子どもは達成感やご褒美があると頑張れるものです。
我が家でも「1ページ終わったらシールを貼る」という仕組みを取り入れたところ、子どもたちのやる気がぐっと上がりました。
シールやスタンプなどの小さなご褒美で十分効果があります。
学習を終えたら「できたね!」「昨日より速くできたね」と褒めることも大切です。
達成感を感じると「またやりたい」という気持ちが芽生え、勉強が前向きな習慣に変わります。
⑥勉強内容を見える化する
- 学習カレンダーを使う:勉強した日は色を塗る or シールを貼る
- チェックリストを作る:今日やる内容をリスト化し、終わったら✓をつける
- ドリルの進捗を見えるように置く:残りページが減ると達成感が得られる
- 目標表を貼り出す:「今月の目標」を書き出し、家族で共有する
- グラフ化する:勉強時間を棒グラフにすると増えていく達成感がある
- シールやスタンプを活用する:視覚的なご褒美でモチベーションUP
- 家族と成果を共有するスペースを作る:冷蔵庫や壁に「今日のがんばり」を掲示
勉強習慣を身につけるには「自分の努力を目で確認できること」が大切です。
学習カレンダーやチェック表を作り、勉強した日は色を塗ったりシールを貼ると、子どもは「続けている!」という実感が持てます。
我が家の子どもたちも、自分でカレンダーにマークをつけるのを楽しみにしており、自然と机に向かう流れができました。
学習の進捗を見える化することで、子どものモチベーションが保ちやすくなります。
⑦親も一緒に机に向かう
特に低学年の子どもは「一人で勉強する」ことが難しいです。
我が家でも下の子は、一人だとすぐに遊びたくなってしまいます。



そこで、私も隣に座って本を読んだり作業をするようにしました。
すると「一緒にやっている」という感覚で安心するのか、集中力が続くようになりました。
親も机に向かう姿を見せることは「勉強するのが当たり前」というメッセージになります。
⑧短時間集中法を取り入れる
「ダラダラ長く」よりも「短時間で集中」が効果的です。
タイマーを使って「5分だけ」「10分だけ」と区切ると、子どもはゲーム感覚で集中できます。
我が家でも「5分チャレンジ」と名付けて取り組んでおり、時間を区切るだけで子どものやる気が上がりました。
短時間集中法は「勉強=疲れる」という感覚をなくし、勉強を始めるハードルを下げる効果があります。
⑨興味を活かした教材を使う
子どもの興味を活かすと勉強は一気に楽しくなります。



我が家ではポケモンのドリルを使ったところ、勉強嫌いの子が「ピカチュウと一緒ならやる!」と自分から取り組むようになりました。
キャラクター教材や無料アプリなど、子どもが「楽しい」と感じる工夫を取り入れることがポイントです。
遊び心があると継続しやすく、習慣化にもつながります。
⑩成果を家族で共有し褒める
勉強習慣を定着させる最後のポイントは「家族で褒めること」です。
我が家では、今日頑張ったことを夕食のときにみんなで共有しています。
「漢字を10個覚えたよ!」「計算が速くなったね!」と声をかけると、子どもは誇らしげにして次の日も頑張ろうとします。
小さな成果を認め合うことで、勉強がポジティブな習慣へと変わっていきます。
小学校で勉強習慣がついたときのメリット
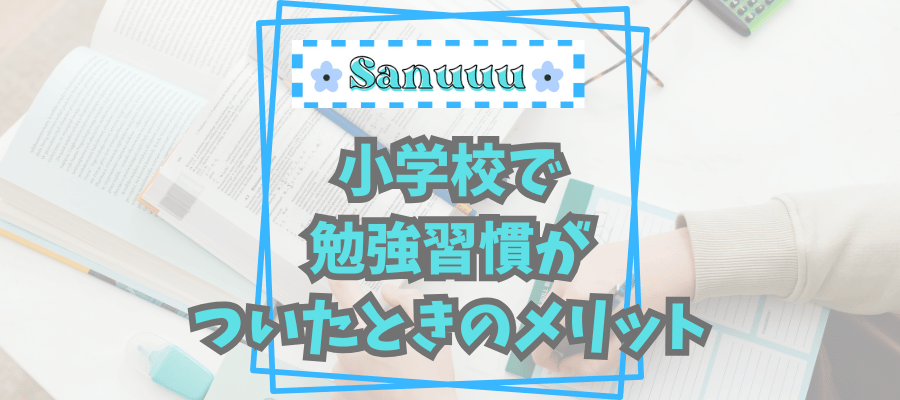
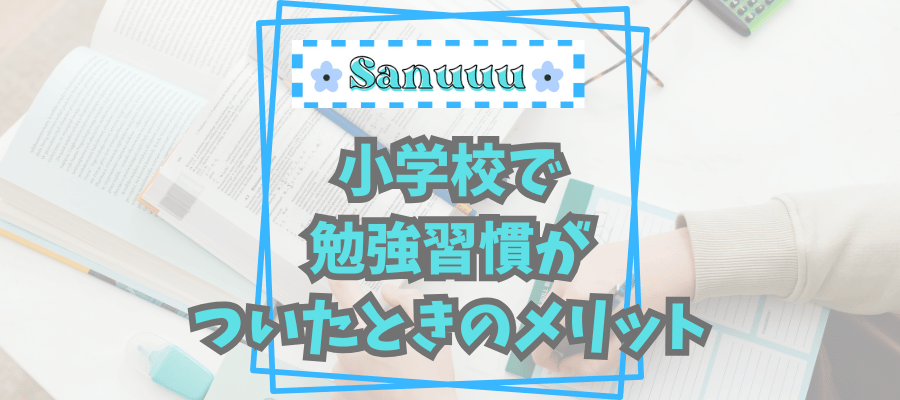
小学生のうちに勉強習慣が定着すると、学力面だけでなく生活面や心の成長にも大きな効果があります。
毎日机に向かうことが「当たり前」になると、勉強を嫌がらずに続けられ、中学・高校での学習にもスムーズにつながります。
私自身、3人の子どもを育てていて、勉強習慣がある子とない子では自信や学力の伸び方に大きな差が出ると感じています。
ここでは、勉強習慣がついたときの3つのメリットを具体的に見ていきましょう。
学力が安定し、中学以降の学習につながるメリット
小学生のうちに勉強習慣がついている子は、基礎学力が自然と身につきます。
毎日の積み重ねで計算や漢字、読解力といった土台が固まるため、中学以降の応用的な学習にも無理なく対応できます。
テスト前に一夜漬けをする必要がなく、自然と準備ができている状態になるのも大きな強みです。
- 基礎学力が定着して忘れにくい
- 中学・高校での学習にスムーズにつながる
- テストや受験で慌てずに済む
| 習慣あり | 習慣なし |
|---|---|
| 毎日コツコツ知識が定着 中学の勉強にもスムーズに移行 | 学習に波があり忘れやすい 応用学習でつまずきやすい |
規則正しい生活リズムや計画性が育つメリット
勉強習慣は「時間を守る」ことにつながるため、生活リズム全体を整える効果があります。
我が家でも「宿題+ドリル1ページ」を固定の時間に取り入れたことで、遊びや習い事との両立がスムーズになりました。
計画的に勉強する経験を積むことで、自然と「やるべきことを先に片付ける」姿勢も育ちます。
- 学校から帰宅後の流れがスムーズになる
- 習い事や遊びと勉強の両立がしやすい
- 計画的に物事を進める力が育つ



つまり、勉強習慣は単なる学力アップではなく「生活習慣の基盤」になるのです。
自信や自己肯定感が高まり、勉強への意欲が増すメリット
毎日勉強を続けると、小さな達成感が積み重なります。
「昨日もできた」「今日もできた」という経験は、子どもの自信につながり、自己肯定感を高めます。
我が家でも、チェック表にシールを貼るだけで子どもたちは誇らしげな顔をしていました。
- 小さな成功体験が自信を育てる
- 「勉強=できる」に意識が変わる
- 勉強を前向きに取り組める
習慣がある子は「やらされる勉強」ではなく「自分からやる勉強」に変わりやすく、将来にわたって学び続ける力が身につきます。
3人の子どもで実践!習慣づけに役立ったテキスト紹介
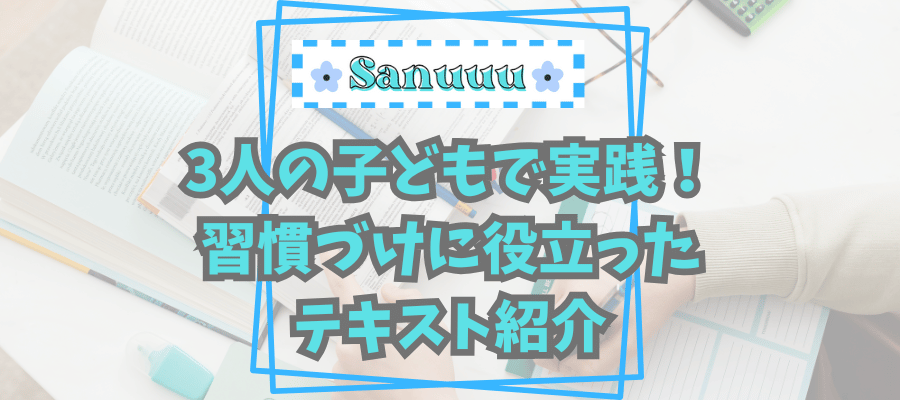
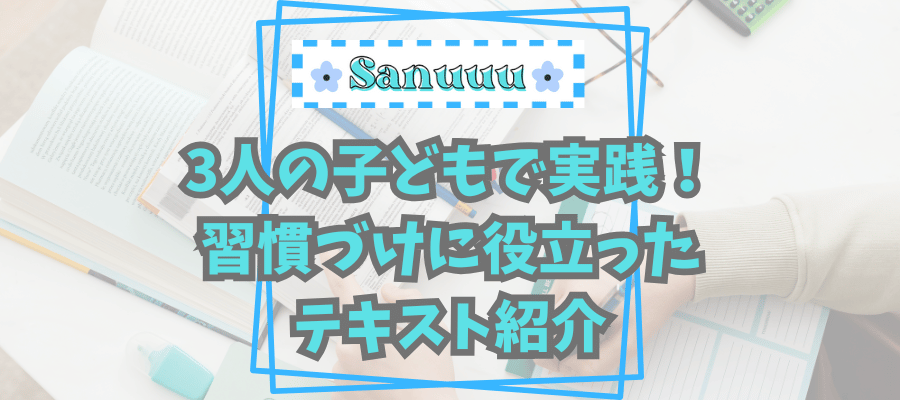
我が家には小学生の子どもが3人いますが、それぞれ性格も得意・不得意も違うため、勉強習慣をつける工夫もバラバラでした。
そこで大切にしたのは「その子に合った教材を選ぶこと」です。
長男には中学を意識した教材を、次男には基礎をしっかり固められるドリルを、末っ子には遊び感覚で楽しめるキャラクター教材を使いました。
勉強習慣は「やる気」だけで続けるのは難しいものですが、子どもが「これならやってみたい」と思える教材を選ぶと、自然と机に向かう時間が増えていきます。
ここでは、我が家の3人の子どもが実際に使ってきたテキストと、その効果についてご紹介します。
高学年の長男が選んだ教材(ポケモン図鑑ドリル)


高学年になると、中学を意識した勉強を進めたいと思う一方で、まだ「楽しく学びたい」という気持ちも強く残っています。
我が家の長男は、もともと勉強にあまり前向きではありませんでしたが、大好きなキャラクターが出てくる「ポケモン図鑑ドリル」をきっかけに机に向かうようになりました。
難しい内容でも「ポケモンと一緒ならやれる!」と前向きな気持ちになれたのが大きな変化です。
- 人気キャラクターで勉強への抵抗感を減らせる
- 1ページごとの分量がちょうどよく達成感が得やすい
- 国語・算数・英語など幅広く学べるラインナップ



楽しく学びながら基礎を固められるため、高学年でも継続しやすい教材です。
ポケモン図鑑ドリルの詳細を確認したい人は下記記事もチェックしてください。
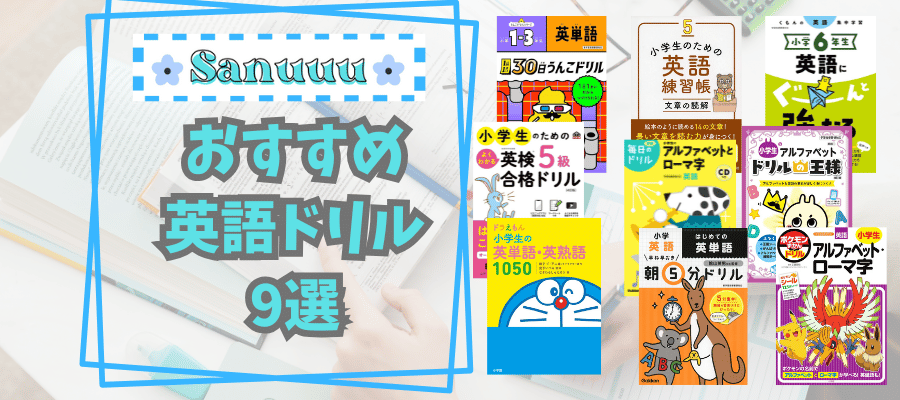
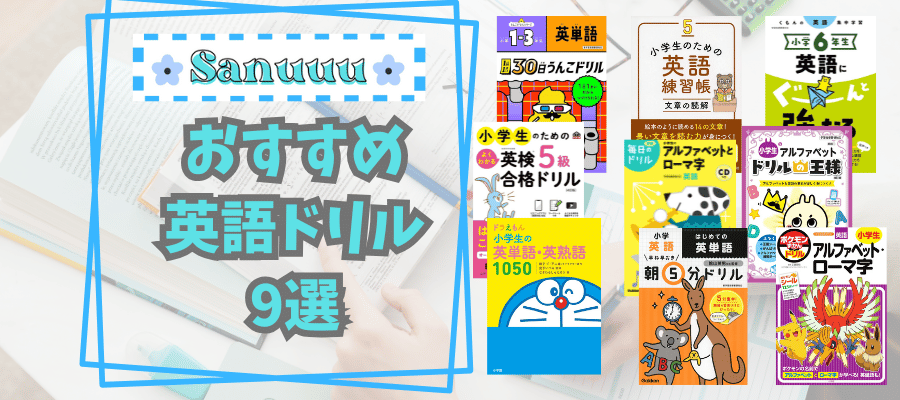
中学年の次男が使っているドリル(毎日のドリル漢字)


中学年は、漢字や計算など基礎をしっかり固めることが大切な時期です。
我が家の次男は集中力が長く続かないタイプですが、「毎日のドリル漢字」は1日1ページで終わる手軽さがちょうどよく、無理なく続けられました。
毎日取り組むことで、自然と漢字の定着度が上がり、学校のテストでも自信を持って答えられるようになっています。
- 1日1ページで取り組みやすい構成
- 書いて覚える形式で漢字の定着に効果的
- 学校の学習進度に合っているため復習に使いやすい



基礎力を固めながら「毎日やる」習慣をつけるのにぴったりのドリルです。
毎日のドリルの詳細を見たい人は下記記事もチェックしてみてください!
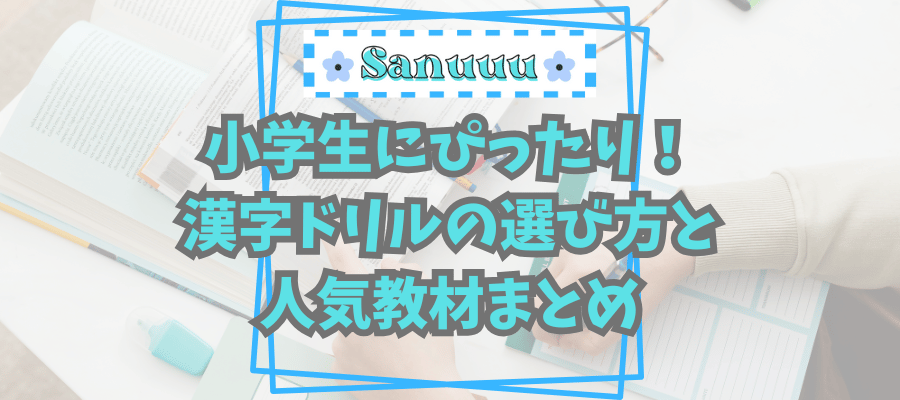
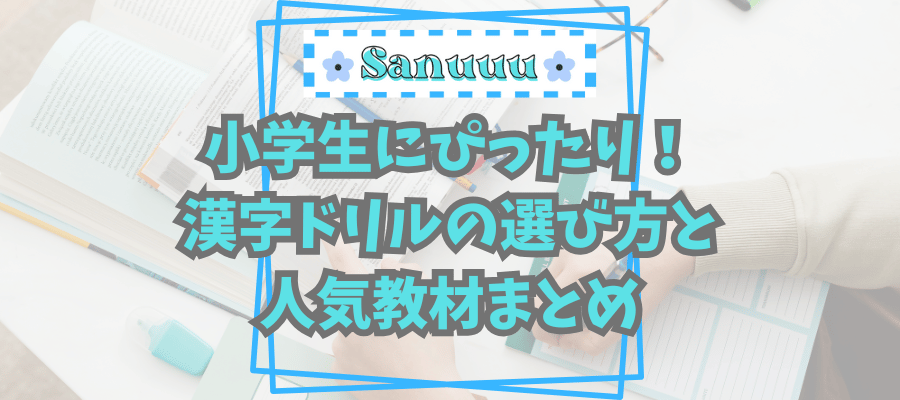
低学年の末っ子がハマったテキスト(くもんの小学ドリル)





低学年はまだ勉強に慣れていないため、「やらされる」感覚が強いと続きません。
我が家の末っ子には「くもんの小学ドリル」を選びました。
内容はとてもシンプルで、基礎の繰り返しに特化しているため、短時間でもしっかり力がつきます。
末っ子も「これならできる!」という達成感を味わえ、シールを貼って進める仕組みを作ったことで毎日楽しみながら取り組めています。
- 基礎を徹底的に繰り返せる構成
- 問題量がちょうどよく「学年×10分学習」に適している
- 子どもが達成感を感じやすいデザイン
勉強が初めての子でも「できた!」を積み重ねられる教材としておすすめです。
くもんの小学生ドリルの詳細は下記の記事もチェックしてみてください。
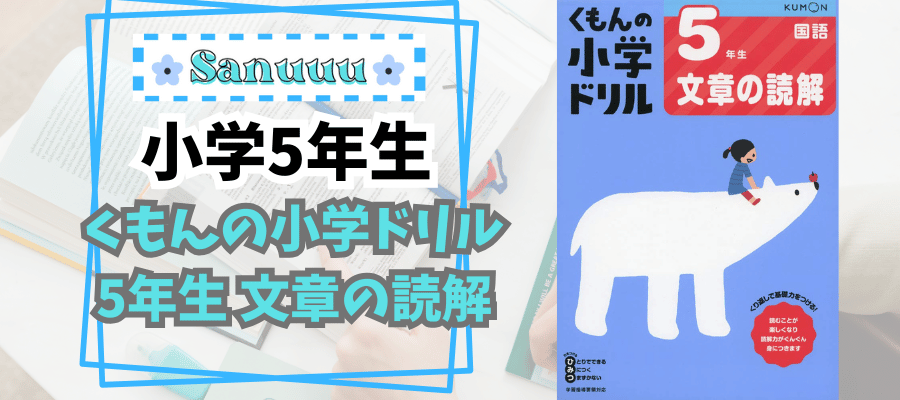
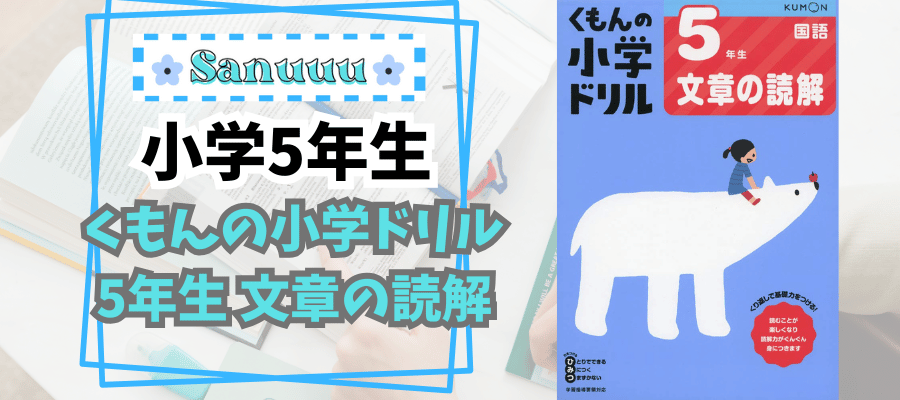
小学生の勉強を習慣づけに関するQ&A
- 宿題だけで本当に大丈夫?
-
宿題は授業の復習として大切ですが、それだけでは基礎が定着しにくいことがあります。
特に応用問題や文章読解、英語などは宿題だけでは不足しがちです。
宿題にプラスして「ドリル1ページ」や「読書10分」を加えるだけで、学習効果がぐっと高まります。
- 勉強時間はどのくらいが目安ですか?
-
小学生の家庭学習は「学年×10分」が基本の目安です。
- 1年生 → 10分
- 3年生 → 30分
- 6年生 → 60分
短くても毎日続けることが大切です。長時間やろうとするよりも、無理なく習慣化できる範囲で進めるほうが効果的です。
- 勉強が苦手な子にどう声をかければいい?
-
「まだできてない」ではなく「ここまでできたね」と成果を認める声かけが効果的です。
我が家でも「昨日より早くできたね!」と褒めることで子どものやる気が上がりました。
小さな成功体験を積み重ねることで、勉強に前向きな気持ちが育ちます。
- どんな教材を選べばいいですか?
-
子どもの性格や学年に合わせた教材選びが大切です。
- 低学年 → キャラクタードリルで楽しく
- 中学年 → 「毎日のドリル」で基礎固め
- 高学年 → 「ぐーんとシリーズ」で応用と中学準備
教材は「子どもが自分からやりたくなるかどうか」を基準にすると続けやすいです。
まとめ 〜勉強習慣は毎日の積み重ねで育つ〜


小学生のうちに勉強習慣を身につけることは、子どもの将来に大きな影響を与えます。
宿題だけで終わらせず、1日10分でも「プラスα」の学習を取り入れることで、基礎学力はもちろん、自信や自己肯定感まで育てることができます。
我が家でも、子どもそれぞれに合ったドリルや教材を取り入れたことで、机に向かう習慣が自然と定着しました。
勉強習慣のポイントは「無理をしないこと」と「続けやすい工夫を取り入れること」です。
キャラクタードリルやアプリを使って楽しく学ぶのも一つの方法ですし、学年×10分を目安に短時間集中で進めるのも効果的です。
大切なのは、毎日コツコツ積み重ねること。
保護者は「勉強を管理する人」ではなく「伴走者」として子どもを支え、一緒に成長を喜び合える存在でありたいですね。
“※当サイトではアフィリエイトプログラムを利用し、商品を紹介しています。
リンクから商品を購入された場合、売上の一部が運営者に還元されることがあります。
読者さまのご負担は変わりませんので、ご安心ください。”